Home > Archive > セイアンアーツアテンション12「Roots Routes Travelers」展評
セイアンアーツアテンション12「Roots Routes Travelers」展評
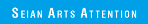
琵琶湖畔の植物たち 「Roots Routes Travelers」展によせて
愛知県美術館 学芸員
中村史子
 セイアンアーツアテンション12 Roots Routes Travelers / 【キャンパスが美術館】ライトギャラリー
セイアンアーツアテンション12 Roots Routes Travelers / 【キャンパスが美術館】ライトギャラリー
本展のテーマとなっているルーツ(Roots)。Rootsはしばしば「起源」や「故郷」を指す。また、この語の単数形であるRootは植物の根も意味する言葉だ。植物の根は、外からは見えない地下へと深く伸び、横へと広がっていく。そして、土中の栄養分を引き揚げ、地上の茎、枝葉、花や果実を生み出す。
本展の出展作家たちの制作過程やその成果である作品を眺めると、「起源」や「故郷」以上に、この植物の根とよく似た構造を持っていることに気づかされる。彼女たちは、不可視の歴史や記憶の層の深くへと手を伸ばし、何かを掴み取る。時に、掴み取ったものが何か判然としない場合もあるが、その分からなさも含め眼前にさらし、そこから次の表現を作り上げるのである。本展は、「起源」や「故郷」であるRootsをテーマにしつつ、5名の作家の根の張り方をみせる展示とも言えよう。具体的にそれぞれの特質を整理してみよう。
それでは、中尾美園を最初に見てみよう。彼女は、先の世代が培ってきた文化を継承し、《うつす、うつる、》という作品タイトルが示す通り、できる限り「うつし」取ろうとする。《うつす、うつる、》では、文字通りしめ縄作りの過程を動画で記録し映すこと、原寸大でしめ縄を描き写すこと、そして、しめ縄作りの技術を自らの身体に移すことが試みられている。
他にも、祖母の着物の切れ端を描き写した《美佐子切》や、知人の親族に当たる女性、久代が持っていた国旗の一部を描き写した《久代切》が展示されている。いずれの作品も、あくまで“物”を巡って先の世代から中尾へと継承が行われているのが特徴だ。また、“物”に伴う文化や風習を断片的でも引き受け、それをそのまま写す/移すことで今に残そうとする姿勢を見てとることが出来る。
中尾同様、先の世代の経験の一部をそのまま再現して見せる点は、井上裕加里に共通している。井上の展示で中心的な位置付けにある映像作品《罪の意識》では、原子爆弾開発に関わった研究者、原子爆弾を広島に投下した飛行機の乗組員、広島の被曝者たちの言葉をそれぞれ作家自身が音読している。 個人的な解釈や改変を入れず、先人たちの言葉を自分自身の体を媒介に再現する姿勢は、中尾とあい通じる。しかし一方で、井上は立場の異なる複数の人物の言葉を対話形式で発話することで、それぞれの言葉のそのあい通じなさ、交差しがたさをも浮かび上がらせる。それによって、一つの事実には収斂しがたい過去の複雑さを、文字通り、自らの身体を通じて批評的に読み解こうとしている。
また、金サジも、自らの身体を過去の記憶を伝える一種の媒介物として扱っている。しかしながら、彼女が井上と大きく異なるのは、先人の経験を直裁に蘇らせることから離れ、自分自身の想像力でありえただろう過去の物語を作り上げている点だ。井上の作品には、歴史的事象の理解し難さが満ちているが、金サジは過去の伝承が自分自身の身体に意識せぬまま沈殿している驚きから出発している。 それゆえか、代表作「物語」シリーズにおいて、彼女は、記憶、そして命を宿すものとしての身体をしばしば主題として被写体を構成し、様々な演出を施して写真を撮る。注目したいのは、彼女の代表作である本シリーズの多くが、その物語も、写真自体も特定の伝承等には必ずしも紐づかない創作物である部分だろう。過去の記憶や経験は、それをそのまま時代の流れに沿って面々と継承されるだけではなく、時に現在から過去への創作や想像も含んだ大きなジャンプによって、鮮明に血の通った形で浮かび上がるのだ。
 【キャンパスが美術館】ライトギャラリー / 中尾美園 / 「うつす、うつる、」
【キャンパスが美術館】ライトギャラリー / 中尾美園 / 「うつす、うつる、」
 【キャンパスが美術館】ギャラリーアートサイト / 井上裕加里 / 「罪の意識」
【キャンパスが美術館】ギャラリーアートサイト / 井上裕加里 / 「罪の意識」
 【キャンパスが美術館】アートサイト前エントランス / 金サジ / 「物語」シリーズ
【キャンパスが美術館】アートサイト前エントランス / 金サジ / 「物語」シリーズ
さて、ここまで紹介した3名は、いずれも作家本人が過去や記憶の受け手となっている。その受け手をより広い射程で捉えているのが吉良加奈子だ。彼女はたまたま見つけた作者不詳の犬のイラストー落書きと言った方が適切かもしれないーの継承者、伝承者となることを勝手に名乗り出る。そして、そのイラストを石ころに描いて道端に置いたり、あるいはグッズ展開して、より多くの人々へと何気なく広めようと努力するのである。
吉良は、犬のイラストが描かれるに至った経緯やその作者、つまりイメージの起源には、あまり重心を置いていないようだ。それよりも、そのイメージとどれだけ自由に戯れられるか、そのイメージがどれだけ遠くまで届きうるかに賭けている。彼女のプロジェクトは、過去を掘り進め何かを探し出そうとするベクトル以上に、今、ここに残されたイメージをどう今後の人々が編集し受容するかというベクトルへと動かされている。
さらに、過去を継承し解釈する主体を、自分自身を超えて人間以外の存在へとも易々と置き換えるのが澤田華である。澤田も吉良も、偶然出会った身元不明のイメージから出発しているが、澤田は吉良と異なり執拗にその正体を追求する。その淡々とした手つきは、どこか鑑識などを彷彿とさせる。
しかしながら、あくまで調査をしている風のプロセスこそが彼女の作品においては肝心なのであり、本当にその正体を把握する気ははなから無さそうだ。20世紀中ばの欧米の室内風景写真に写り込んだ謎の円形の突起を、ハンドスピナーや香炉ではないかと、彼女は予測するくらいなのだから。さらに、パソコンの自動認識システムは、そのイメージを似ても似つかない海外の芸能人だと名指して憚らない。 これら一連の行為から、起源はいくらでも後から作り替えられること、その誤読が連鎖してゆく自由さ、そして、誤読の機会は今ここに生きる人以外にも開かれていることが、確認される。「これは〜です」と未知のイメージの正体について機械的に繰り返す声は、先述した作家の表現を特徴付けていた身体性とは異なる肌理を持っている。もっと、不気味で、しかし乾いたユーモアも備えている。
 【キャンパスが美術館】ギャラリーウィンドウ / 吉良加奈子 / 「旅する犬」
【キャンパスが美術館】ギャラリーウィンドウ / 吉良加奈子 / 「旅する犬」
 【キャンパスが美術館】ギャラリーキューブ / 澤田華 / 「Gesture of Rally #1902」
【キャンパスが美術館】ギャラリーキューブ / 澤田華 / 「Gesture of Rally #1902」
最初、私はRootsは起源、故郷であり、その単数形であるRootは植物の根だと書いた。根なし草、あるいは根をはる、という言い回しに顕著なように、Rootに基づく表現は特定の場所やコミュニティー、文化との確かな結びつきを想起させる。しかしながら、植物は根から吸い上げた養分で実を結び、その種は様々な偶然の末に全く別の場所へと運ばれ、そこで再び根をはる。それは、今ここにたまたま残された物に対する解釈やその受容の自由さをも保証するのではないか。長い時を超えて種が芽を出すように、過去の事物を今、生きている身体が蘇えらせる。それと同時に、拡散する種子のように、元々の場所からいくらでも離れ、時には分裂し複数化しながら全く未知の形へと広がりゆく。本展は、その双方の動態を確かに感じさせるものではないだろうか。
(2019.11.12)
愛知県美術館 学芸員
中村史子
 セイアンアーツアテンション12 Roots Routes Travelers / 【キャンパスが美術館】ライトギャラリー
セイアンアーツアテンション12 Roots Routes Travelers / 【キャンパスが美術館】ライトギャラリー
本展のテーマとなっているルーツ(Roots)。Rootsはしばしば「起源」や「故郷」を指す。また、この語の単数形であるRootは植物の根も意味する言葉だ。植物の根は、外からは見えない地下へと深く伸び、横へと広がっていく。そして、土中の栄養分を引き揚げ、地上の茎、枝葉、花や果実を生み出す。
本展の出展作家たちの制作過程やその成果である作品を眺めると、「起源」や「故郷」以上に、この植物の根とよく似た構造を持っていることに気づかされる。彼女たちは、不可視の歴史や記憶の層の深くへと手を伸ばし、何かを掴み取る。時に、掴み取ったものが何か判然としない場合もあるが、その分からなさも含め眼前にさらし、そこから次の表現を作り上げるのである。本展は、「起源」や「故郷」であるRootsをテーマにしつつ、5名の作家の根の張り方をみせる展示とも言えよう。具体的にそれぞれの特質を整理してみよう。
それでは、中尾美園を最初に見てみよう。彼女は、先の世代が培ってきた文化を継承し、《うつす、うつる、》という作品タイトルが示す通り、できる限り「うつし」取ろうとする。《うつす、うつる、》では、文字通りしめ縄作りの過程を動画で記録し映すこと、原寸大でしめ縄を描き写すこと、そして、しめ縄作りの技術を自らの身体に移すことが試みられている。
他にも、祖母の着物の切れ端を描き写した《美佐子切》や、知人の親族に当たる女性、久代が持っていた国旗の一部を描き写した《久代切》が展示されている。いずれの作品も、あくまで“物”を巡って先の世代から中尾へと継承が行われているのが特徴だ。また、“物”に伴う文化や風習を断片的でも引き受け、それをそのまま写す/移すことで今に残そうとする姿勢を見てとることが出来る。
中尾同様、先の世代の経験の一部をそのまま再現して見せる点は、井上裕加里に共通している。井上の展示で中心的な位置付けにある映像作品《罪の意識》では、原子爆弾開発に関わった研究者、原子爆弾を広島に投下した飛行機の乗組員、広島の被曝者たちの言葉をそれぞれ作家自身が音読している。 個人的な解釈や改変を入れず、先人たちの言葉を自分自身の体を媒介に再現する姿勢は、中尾とあい通じる。しかし一方で、井上は立場の異なる複数の人物の言葉を対話形式で発話することで、それぞれの言葉のそのあい通じなさ、交差しがたさをも浮かび上がらせる。それによって、一つの事実には収斂しがたい過去の複雑さを、文字通り、自らの身体を通じて批評的に読み解こうとしている。
また、金サジも、自らの身体を過去の記憶を伝える一種の媒介物として扱っている。しかしながら、彼女が井上と大きく異なるのは、先人の経験を直裁に蘇らせることから離れ、自分自身の想像力でありえただろう過去の物語を作り上げている点だ。井上の作品には、歴史的事象の理解し難さが満ちているが、金サジは過去の伝承が自分自身の身体に意識せぬまま沈殿している驚きから出発している。 それゆえか、代表作「物語」シリーズにおいて、彼女は、記憶、そして命を宿すものとしての身体をしばしば主題として被写体を構成し、様々な演出を施して写真を撮る。注目したいのは、彼女の代表作である本シリーズの多くが、その物語も、写真自体も特定の伝承等には必ずしも紐づかない創作物である部分だろう。過去の記憶や経験は、それをそのまま時代の流れに沿って面々と継承されるだけではなく、時に現在から過去への創作や想像も含んだ大きなジャンプによって、鮮明に血の通った形で浮かび上がるのだ。
 【キャンパスが美術館】ライトギャラリー / 中尾美園 / 「うつす、うつる、」
【キャンパスが美術館】ライトギャラリー / 中尾美園 / 「うつす、うつる、」 【キャンパスが美術館】ギャラリーアートサイト / 井上裕加里 / 「罪の意識」
【キャンパスが美術館】ギャラリーアートサイト / 井上裕加里 / 「罪の意識」 【キャンパスが美術館】アートサイト前エントランス / 金サジ / 「物語」シリーズ
【キャンパスが美術館】アートサイト前エントランス / 金サジ / 「物語」シリーズさて、ここまで紹介した3名は、いずれも作家本人が過去や記憶の受け手となっている。その受け手をより広い射程で捉えているのが吉良加奈子だ。彼女はたまたま見つけた作者不詳の犬のイラストー落書きと言った方が適切かもしれないーの継承者、伝承者となることを勝手に名乗り出る。そして、そのイラストを石ころに描いて道端に置いたり、あるいはグッズ展開して、より多くの人々へと何気なく広めようと努力するのである。
吉良は、犬のイラストが描かれるに至った経緯やその作者、つまりイメージの起源には、あまり重心を置いていないようだ。それよりも、そのイメージとどれだけ自由に戯れられるか、そのイメージがどれだけ遠くまで届きうるかに賭けている。彼女のプロジェクトは、過去を掘り進め何かを探し出そうとするベクトル以上に、今、ここに残されたイメージをどう今後の人々が編集し受容するかというベクトルへと動かされている。
さらに、過去を継承し解釈する主体を、自分自身を超えて人間以外の存在へとも易々と置き換えるのが澤田華である。澤田も吉良も、偶然出会った身元不明のイメージから出発しているが、澤田は吉良と異なり執拗にその正体を追求する。その淡々とした手つきは、どこか鑑識などを彷彿とさせる。
しかしながら、あくまで調査をしている風のプロセスこそが彼女の作品においては肝心なのであり、本当にその正体を把握する気ははなから無さそうだ。20世紀中ばの欧米の室内風景写真に写り込んだ謎の円形の突起を、ハンドスピナーや香炉ではないかと、彼女は予測するくらいなのだから。さらに、パソコンの自動認識システムは、そのイメージを似ても似つかない海外の芸能人だと名指して憚らない。 これら一連の行為から、起源はいくらでも後から作り替えられること、その誤読が連鎖してゆく自由さ、そして、誤読の機会は今ここに生きる人以外にも開かれていることが、確認される。「これは〜です」と未知のイメージの正体について機械的に繰り返す声は、先述した作家の表現を特徴付けていた身体性とは異なる肌理を持っている。もっと、不気味で、しかし乾いたユーモアも備えている。
 【キャンパスが美術館】ギャラリーウィンドウ / 吉良加奈子 / 「旅する犬」
【キャンパスが美術館】ギャラリーウィンドウ / 吉良加奈子 / 「旅する犬」 【キャンパスが美術館】ギャラリーキューブ / 澤田華 / 「Gesture of Rally #1902」
【キャンパスが美術館】ギャラリーキューブ / 澤田華 / 「Gesture of Rally #1902」最初、私はRootsは起源、故郷であり、その単数形であるRootは植物の根だと書いた。根なし草、あるいは根をはる、という言い回しに顕著なように、Rootに基づく表現は特定の場所やコミュニティー、文化との確かな結びつきを想起させる。しかしながら、植物は根から吸い上げた養分で実を結び、その種は様々な偶然の末に全く別の場所へと運ばれ、そこで再び根をはる。それは、今ここにたまたま残された物に対する解釈やその受容の自由さをも保証するのではないか。長い時を超えて種が芽を出すように、過去の事物を今、生きている身体が蘇えらせる。それと同時に、拡散する種子のように、元々の場所からいくらでも離れ、時には分裂し複数化しながら全く未知の形へと広がりゆく。本展は、その双方の動態を確かに感じさせるものではないだろうか。
(2019.11.12)